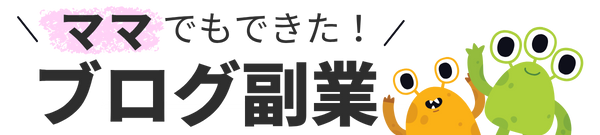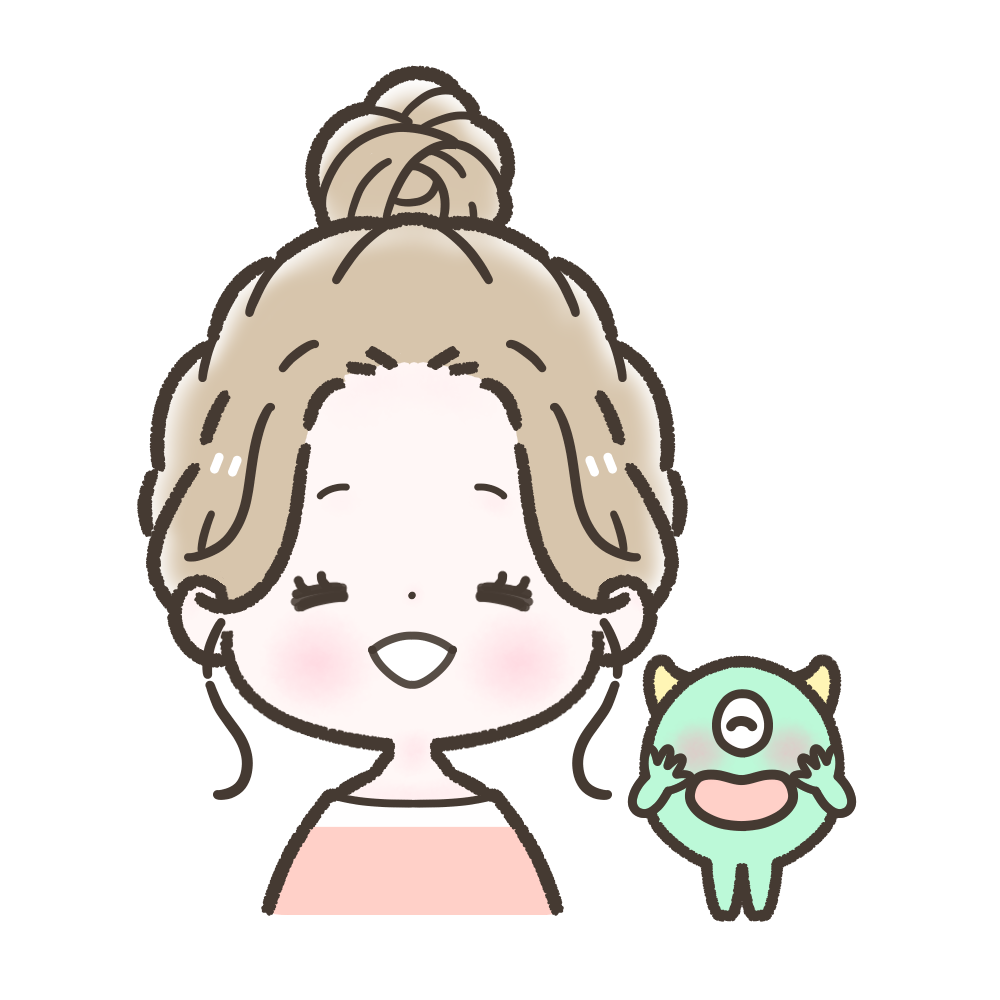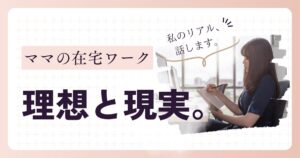こんにちは。ひなたママです。
「ブログを書きたいのに時間がない」
「スキマ時間ができても何から手をつけていいか分からない」
「モチベーションが続かない…」
そんな風に感じていませんか?

ママにとってのブログ運営は、時間との戦いですよね。
言うことを聞かない子供たちに、毎日のご飯作りや、溜まった家事。
でも。
- せっかく始めたブログを諦めたくない!
- 限られた時間で効率的に記事を書きたい!
そこで、
- もっと読まれるブログに育てたいけど、まずは継続が課題…
- 育児とブログの両立って、本当にできるの?
そんな切実な想いを抱えているママのために、
- 「具体的にどんな方法で時間を捻出しているの?」
- 「忙しいママでも本当に実践できるテクニックが知りたい」
- 「モチベーションが落ちた時の対処法は?」
- 「ブログを継続するための裏ワザってある?」
というお悩みについて、今回は書いていきたいと思います!
この記事を読むとわかること
「ブログ時間が確保できない」という悩みを解決策が見つかり、忙しい育児の合間でもブログを楽しく、そして効率的に継続できるヒントが得られるはずです。
具体的には、
- 時間を有効活用する工夫
- 記事執筆の効率化
- モチベーションを維持する秘訣
まで、現役ママブロガーが実践し効果を実感した「マル秘テクニック」を厳選してご紹介します。
私について
- 私自身も、小さな子どもを育てながらブログ運営している現役ママブロガーです。
- ブログ開設当初は、正直「いつ書けばいいの!?」と絶望することもありました。毎日時間に追われ、ブログを諦めかけたことも何度もあります。
- しかし、様々な工夫を凝らし、効率化ツールや時間管理術を取り入れることで、今ではコンスタントにブログを更新できるようになりました!
私自身が試行錯誤して見つけた「時間と心を守る継続術」をぜひ受け取って下さい。
【必見10選】ママがブログを続けるスキマ時間テクニック

【時間活用編】わずかな時間を味方につける!
子育て中のママにとって、まとまった時間を確保するのは至難の業です。
しかし、わずかなスキマ時間を意識的に活用するだけで、ブログを書く時間は劇的に増えます!
この章では、忙しい日々の合間を縫ってブログ時間を生み出す具体的なテクニックをご紹介します。
テクニック1:早朝「朝活」で静かな集中タイムを確保!

朝活は、ママのブログ時間を生み出す最強の手段です。
なぜ朝活がママブロガーに最適なのか、その理由を3つご紹介しますね。
- 家族が寝静まっているため、邪魔されずに集中できる
- 一日の始まりにブログ作業を終えることで、精神的なゆとりが生まれる
- 集中力が高く、効率的に作業が進む
私も子どもが早く寝たからといって夜更かしして執筆していましたが、やはり寝不足は、全てのクオリティを落とすことに気づきました。
イライラしやすくなるし。とにかく日中は眠い。
なので、朝がおすすめです!
短時間でも集中して取り組めば、想像以上にブログが進みますよ。
具体的には、以下のような「朝活」をおすすめします。
- いつもより30分~1時間早く起きて、簡単なネタ出しや構成作成に当てる。
- 前日の夜に翌朝やることを決めておく。
- コーヒー片手に、好きな音楽を聴きながらリラックスして作業する。
「早起きが苦手で続かないかも…」
そんな風に感じるママも多いのではないでしょうか?
大丈夫です!まずは週に1回、15分からなど、無理のない範囲で試してみましょう。
小さな成功体験が継続の鍵になります。そして、何よりも大切なのは十分な睡眠。
早起きのためには、まず「早く寝る」ことから始めてみましょう。
テクニック2:お昼寝時間で集中!メリハリブログタイム

子どもがお昼寝している時間は、ブログ作業の集中タイムとして最適です!
- 子どもが寝ている間は邪魔が入らず、集中して作業に取り組める
- 短時間でもまとまった時間が確保しやすく、記事の執筆や構成練りなど、集中力が必要な作業に適している
- 夜の睡眠時間を削ることなく、日中にブログを進められるため、寝不足やイライラを防げる
実際に、お昼寝時間を活用するためのコツをご紹介します。
- 子どものお昼寝開始直後から、タイマーをセットして「この時間はブログ!」と決める。
- お昼寝前に、今日のブログでやることを決めておく(例:導入文を書く、キーワードリサーチをするなど)。
- 集中力維持のため、温かい飲み物を用意するなど、自分なりのルーティンを作る。
「うちの子、お昼寝しない日もあるし、寝てもすぐ起きちゃうんだけど…」
というお子さんもいらっしゃいますよね。
お昼寝が安定しない日や、そもそもお昼寝しないお子さんの場合は、他のスキマ時間(テクニック4の細切れ時間など)を積極的に活用しましょう。
完璧を目指さず、できる時にできることをするのが継続のコツです。
テクニック3:「ながら作業」でスキマを有効活用!
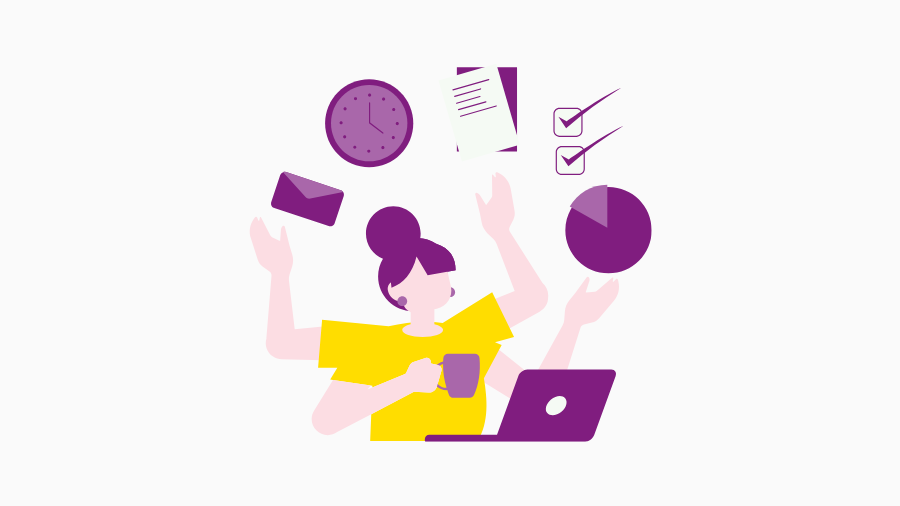
ながら作業は、時間を最大限に活用する賢い方法です。
- 複数の作業を同時に進めることで、効率が格段に上がる
- 無駄な時間を減らし、ブログ以外のタスクもスムーズにこなせる
- 日常の行動がブログのネタ探しや構成練りに繋がる
では、どんな「ながら作業」かというと、
- 料理中:スマホで音声入力を使い、記事のアイデアをメモ。
- 洗濯物を畳みながら:記事の構成を頭の中で組み立てる。
- 子どもの公園遊び中:スマホで市場調査やキーワードリサーチ。
- 授乳中:スマホで読者の「知りたい」ことをリストアップする。
このように、日々のスキマ時間を使って、ブログを少しずつ進められますよ。
ながら作業だと、「集中できないのでは?」
心配になりますよね。
でも大丈夫!あくまで「ながら作業」はインプットやアイデア出しに限定し、集中力が必要な執筆作業はまとまった時間に行う、と使い分けましょう。
テクニック4:細切れ時間を「ブログ貯金」に!

短い細切れ時間でも、有効活用すれば大きな成果に繋がります。
- わずかな時間でも積み重ねることで、ブログ作業の進行に繋がる
- 「今できること」を見つける習慣がつき、時間管理能力が向上する
- どんなに忙しくてもブログに触れる機会が増え、モチベーションを維持しやすくなる
例えば、こんな細切れ時間でブログを進められますよ。
- 子どものお昼寝中(15分):記事のタイトルを5個考える。
- 病院の待ち時間(10分):読みたい競合ブログを1記事読む。
- 電車での移動中(20分):執筆中の記事の誤字脱字チェック。
たった数分でも、これだけブログを前進させることができます。
「そんな短い時間じゃ何もできない…」
そんなことはないです。
短時間でも「特定のタスク」に絞れば十分成果が出ます。
「完璧に終わらせる」のではなく、「一歩でも前に進める」という意識で取り組んでみましょう。
テクニック5:週末に「まとめ書き」でストックを作ろう!
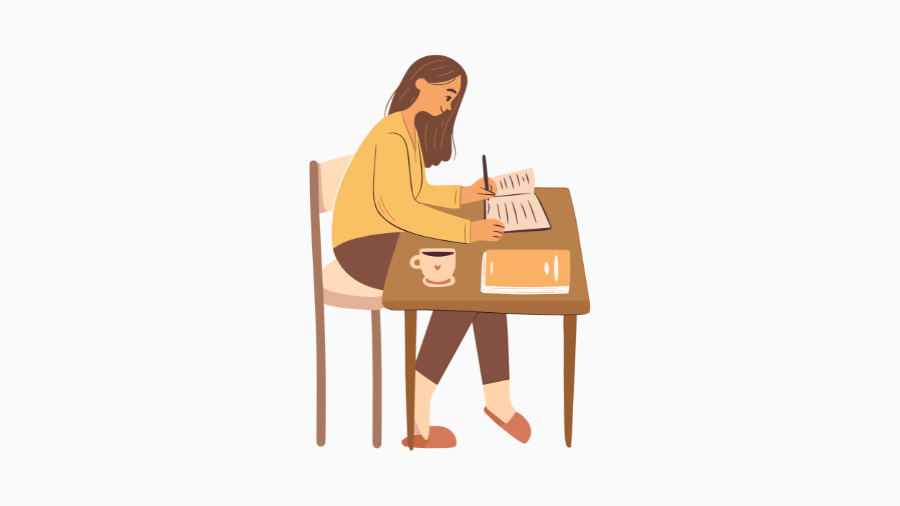
まとめ書きは、週中の余裕を生み出す強力な戦略なので、ぜひ取り入れてみてくださいね。
- まとまった時間で集中して執筆することで、記事の品質が向上する
- 週中に記事公開のプレッシャーから解放され、心にゆとりが生まれる
- 急な用事が入っても、ブログ更新が滞る心配がなくなる
これらのメリットを最大限に活かすための具体的な方法は次の通りです。
- 土日のどちらか半日をブログDAYと決め、2~3記事分の構成作成や執筆を行う。
- 家族の協力(夫に子どもを見てもらうなど)を仰ぎ、集中できる環境を作る。
- 書き溜めた記事は、予約投稿機能を使って計画的に公開する。
計画的にまとめることで、日々のブログへの負担を大きく減らせるはずです。
「週末も忙しくて時間が取れない…」
そんな時は、完璧に数記事分でなくても、「構成だけ」「見出しだけ」でもOK!
まとまった時間が取れない週は、他のテクニックで補いましょう。
【執筆効率化編】サクッと書いて投稿しよう!
時間を見つけても、「いざ書こうとすると手が止まる」「なかなか書き終わらない」と悩んでいませんか?
この章では、限られた時間で効率的に記事を書き上げ、スムーズに公開するための実践的なテクニックをお伝えします!
サクッと執筆して、ブログ更新の喜びを増やしましょう!
テクニック6:記事の「構成」から先に作る!

構成を作ることは、執筆中の迷いをなくし記事の完成度を高める「最短ルート」です。
- 記事の全体像が明確になり、途中で迷うことがなくなる
- 必要な情報を漏れなく盛り込める
- 論理的で分かりやすい記事が書けるようになる
それでは、具体的にどのように構成を作っていけばいいのか見ていきましょう!
- まず「導入・結論・各見出し(h2, h3)」だけ箇条書きで書き出す。
- 各見出しの下に「伝えたいこと」「必要な情報」をメモする。
- 無料の構成作成ツール(Googleドキュメントなど)を活用する。
このステップを踏むだけで、その後の執筆が驚くほどスムーズになりますよ。
「構成を考えるのが面倒…」
と感じるかもしれません。
でも大丈夫!最初は手間取るかもしれませんが、慣れると驚くほど執筆時間が短縮されますよ。
最初は手間取るかもしれませんが、慣れれば執筆時間の短縮に繋がります。
簡単なメモ程度から始めてみましょう!
テクニック7:音声入力を活用して執筆速度を2倍に!

音声入力は、タイピングが苦手なママの救世主です。
- タイピングよりも話す方が速いため、圧倒的に執筆スピードが上がる
- 手が疲れないため、長時間の作業でも疲れにくい
- 頭の中のアイデアをそのまま文字にできるため、思考を中断させない
以上のようなメリットがあります。
それでは、あなたも今日から実践できる「音声入力」の活用術をご紹介しますね!
- スマホの音声入力機能(Googleドキュメント、iPhoneのメモ機能など)を使う。
- PCの場合は、Googleドキュメントの音声入力機能がおすすめ。
- まずは、考えたことを話す練習から始めてみる。
この方法なら、忙しいママでもサクッと記事の土台を作れますよ。
「誤変換が多くて結局修正に時間がかかりそう…」
心配になりますよね。
でも大丈夫!最初は多少の修正は必要ですが、慣れると精度が上がってきます。
まずは「ざっくり下書き」として活用し、後から修正する形で取り組んでみましょう。
テクニック8:テンプレート化で時短!
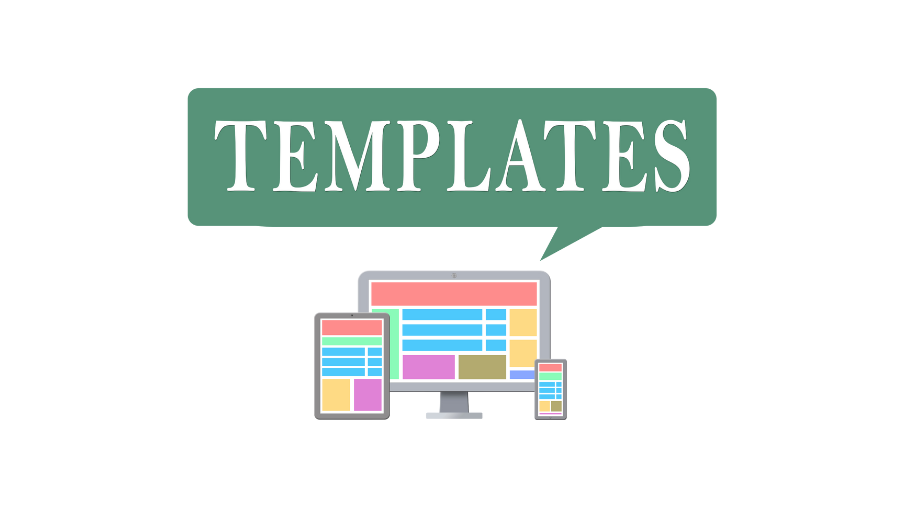
毎回ゼロから記事を書くのは、想像以上に時間がかかりますよね。
でも、テンプレートを上手に活用すれば、執筆時間を大幅に短縮できますよ。
- 記事ごとにゼロから作成する手間が省ける
- ブログ全体のトンマナや構成が統一され、読者にとっても読みやすくなる
- 導入やまとめなど、決まった型を何度も書く時間を削減できる
具体的なテンプレート活用のポイントを見ていきましょう!
- 記事の「導入」「まとめ」「CTA(行動喚起)」の部分をあらかじめ作成しておく。
- アフィリエイトリンクの挿入ブロックや、定型文などをテンプレートとして保存しておく。
- WordPressの「再利用ブロック」機能を活用する。
テンプレートを一度作れば、今後の記事作成がグッと楽になりますよ。
「毎回同じような記事になりそうで心配…」
テンプレートはあくまで骨組みです。
中身のコンテンツは毎回オリジナルなので、個性が失われることはありません。
テクニック9:完璧主義は一旦お休み!「6割完成」で公開する勇気

「もっと良くしたい」
「まだ完璧じゃない」と、
ブログ記事の公開をためらって、せっかく書いた記事が下書きのまま…ということはありませんか?
実は、かつての私も、この『 完璧主義 』に囚われていました。
デザインや記事内容など、自分が納得いくまで徹底的にこだわりすぎて、いつの間にか、そこまで時間をかける必要のない部分に貴重な時間を費やしてしまっていたんです。
知らず知らずのうちに、「完璧主義」の思考に陥っていたんだなと。
完璧を求めすぎると、せっかくのあなたの努力が日の目を見ないままになってしまいますよ。
なぜ、完璧主義を辞めるといいのかその理由は、
- 完璧を求めすぎると、いつまで経っても記事が公開で来ません
- まず公開することで、Googleからの評価や読者の反応を早く得られます
- ブログは「育てるもの」。公開後にいつでも改善できる!
この「6割完成」の考え方を実践するためのヒントは、
- 誤字脱字のチェックはするが、表現の細かなニュアンスは後回し。
- 画像は後から追加できるので、まずはテキスト執筆に集中する。
- 「まずは公開!」を目標に、ハードルを下げてみる。
「公開」することで、あなたのブログは確実に成長していきます。
「未完成な記事を出すのは抵抗がある…」
安心して下さい。
読者は、あなたの記事の「完璧さ」よりも「役立つ情報」を求めています。
まずは情報提供を優先し、読者の反応を見ながらブラッシュアップしていきましょう。
テクニック10:外注やAIツールの活用も視野に入れる!

ブログ継続は、一人で抱え込む必要はありません。
時には外部の力を借りて、効率を大幅にアップさせることも考えるといいです。
- 自分の苦手な部分や時間のかかる作業を効率化できる
- 自分の得意な作業に集中でき、生産性が向上するから
- 新しい技術やサービスを取り入れることで、ブログ運営の幅が広がる
では、具体的にどんな場面で外部の力を借りられるのか見ていきましょう。
- 記事作成の外注:クラウドソーシングサイトで、記事の一部や全部をライターに依頼する。
- 画像作成の外注:アイキャッチ画像や図解などをデザイナーに依頼する。
- AIライティングツールの活用:記事のタイトル案、見出し案、文章のドラフト作成などにChatGPTなどのAIツールを使う。
賢く頼ることで、もっと楽しくブログを続けられますよ。
「お金がかかるから無理…」
確かに、費用は気になるポイントですよね。
でも、ご安心ください。
無料や低価格で利用できるサービスも多くあります。
例えば、無料で使える画像作成ツールのCanvaや、アイデア出しに役立つChatGPTの無料版などから試してみるのもありです。
あなたの時間と労力を節約できるはずですよ。
まとめ:あなたのペースで「継続」を叶えよう!

ブログ継続はマラソン。
無理なく、あなたのペースで走り続けることが大切です。
小さな工夫の積み重ねが、あなたのブログを強く育ててくれます。
まずは、あなたが一番「これならできるかも!」と感じたテクニックを一つ、
明日の朝、お子さんのお昼寝中に試してみませんか?