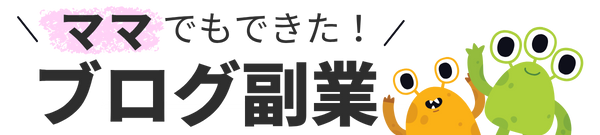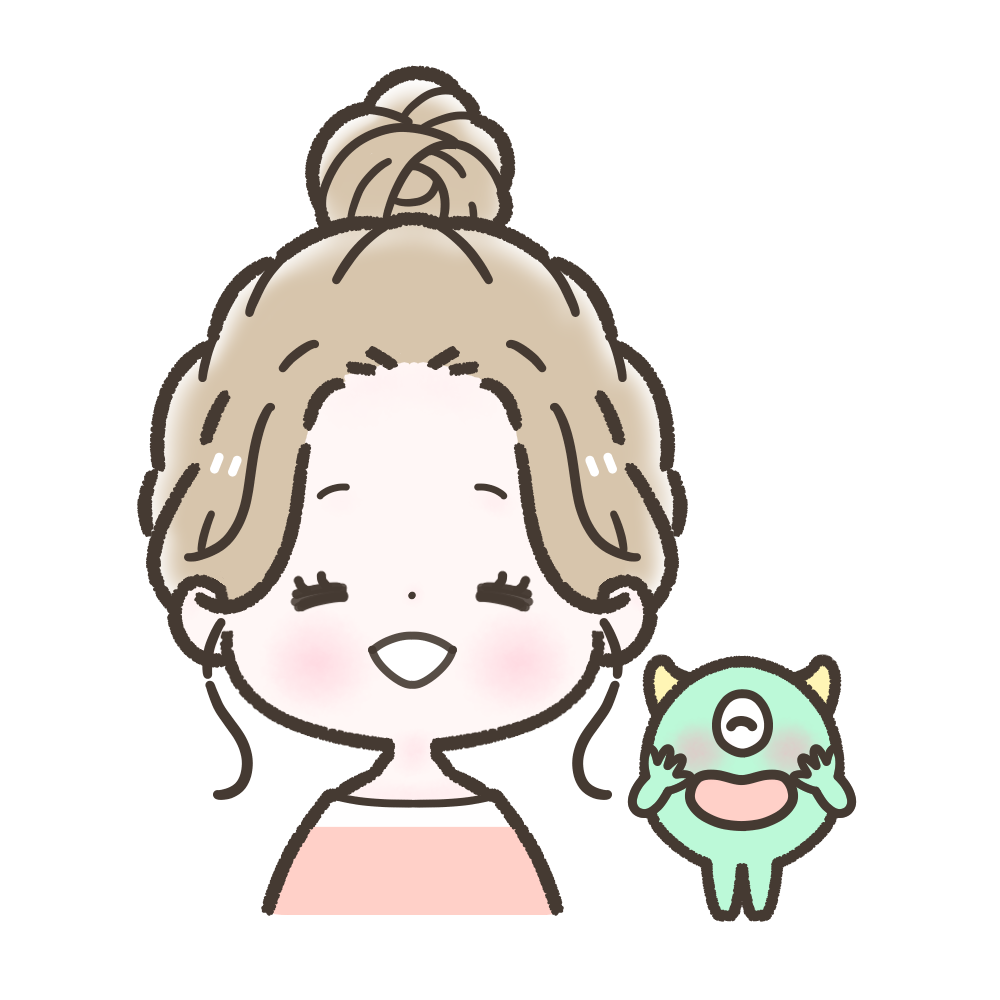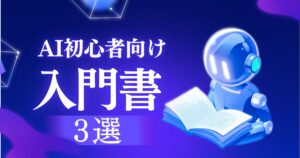こんにちは!
ひなたママです。
今日は、AIの豆知識コラムを書きます。
今回のテーマは、「 AIがなぜ嘘をつくのか 」です。
- 「これって信じていいの?」
- 「どうすれば見分けられるの?」
- 「AIに嘘をつかせない方法ってあるの?」
こういった疑問に答えます。
この記事を読むことで、あなたは
- AIがなぜ間違ったことを言うのか
- その見分け方
- 間違わせないコツ
が理解できるようになります。
日常でAIをもっと安心して使えるようになると、
- 検索するより早く答えが出せる!
- 副業やブログの作業効率がアップする!
と、活用の幅がぐっと広がっていきますよ。
筆者について
私は2023年にプログラミングスクールの24週フリーランスコースを受講し、ChatGPTやGeminiを活用しながら1年半ほどAIと向き合ってきました。
ブログや副業にもAIを積極的に取り入れており、日々の実践から学んだ経験をもとに、わかりやすくお伝えします。
AIが嘘をつくって本当?
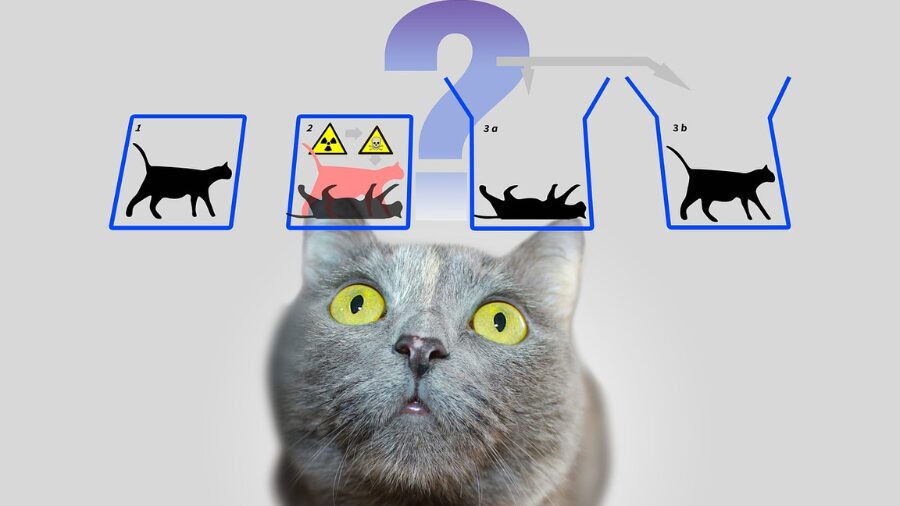
最近、AI(ChatGPTなど)を使っていて、
- 「なんか変なこと言ってるな…」
- 「堂々と間違ったことを教えてくる」
- 「自信たっぷりな回答なのに、あとで間違いだと気づいてショック…」
こんな経験、ありませんか?
私自身も、AIを使いはじめたころに「AIって正しいことしか言わないはず」と思い込んでいました。
でも実際には、まるで本当のように間違った情報を出してくることがあります。
とくに初心者さんだと、
- 「これって信じていいの?」
- 「どうすれば見分けられるの?」
- 「AIに嘘をつかせない方法ってあるの?」
と不安になる方も多いと思います。
今回は、そんな「 AIが嘘をつく問題 」について、わかりやすくお話ししますね。
なぜAIは“堂々と間違う”のか?
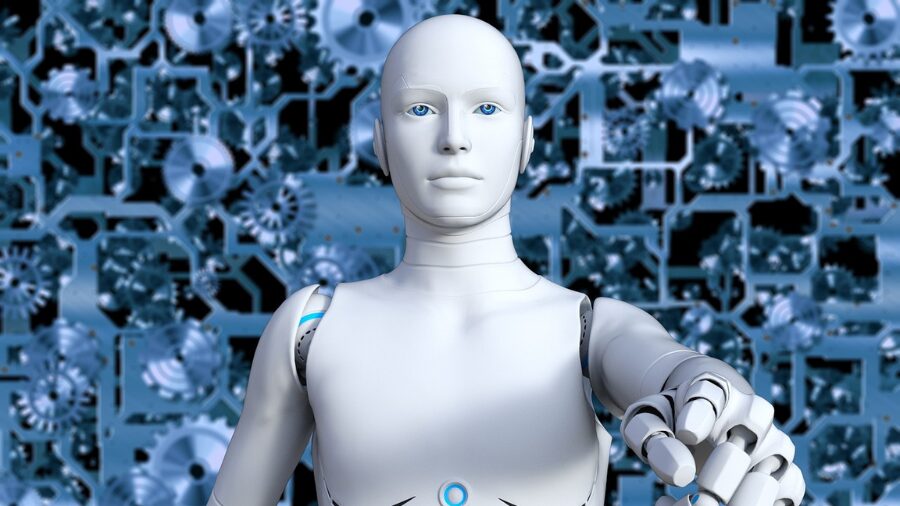
理由①:AIは「予測」しているだけ
AI、特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、統計的にもっともらしい文章を作っているだけです。
つまり「正しいから答えている」のではなく、「この言葉のあとに来そうなもの」を予測しているだけ。
なので、必ずしも正しいとは限らないのです。
理由②:学んでいる情報に間違いが含まれている
ChatGPTは、インターネット上の膨大なデータを学習しています。
でも、ネットの情報って、古かったり、間違っていたり、偏っていたりすることもありますよね。
つまり、情報の出どころも玉石混交。
当然、AIもそういった誤った情報を「もっともらしく」出してくることがあります。
理由③:文体が自信満々なので「正しそう」に見える
AIの回答は、丁寧で断定的。
だからこそ、つい信じてしまいがちなんです。
たとえ間違っていても、それに気づけないケースも多くあります。
理由④:だから「ハルシネーション(幻覚)」が起こる
このように、AIがまるで本当のようにウソを言ってしまう現象のことを「ハルシネーション(幻覚)」といいます。
私がこの言葉を知ったのは、以下の本からでした。
- 『人工知能は人間を超えるか』(松尾豊 著)
- 『生成AIパスポート公式テキスト 2024』(生成AI活用普及協会 監修)
AIを使うなら、この概念を知っておくことはとても大切です。
初心者にもわかりやすく、AIの仕組みと注意点を学べます。
筆者の体験:AIの間違いに気づいたときのこと

私は、2023年にプログラミングスクールで24週のフリーランスコースを受講しました。
その中でChatGPTを使って、コードのアイデアを出したり、エラーの原因を一緒に探ったりしていました。
でもその過程で、
- 回答が間違っていたり、
- 存在しない関数名を提案されたり、
- まったく動かないコードを教えられたり、
…など、「あれ?おかしいな」と思う場面がたくさんありました。
最近、実際に起きた「存在しない情報」の例
たとえば、私は「存在しない本をタイトル付き」で紹介されたことがあります。
いくら探しても見当たらないので、不思議に思い、AIに尋ねてみました。
その返答がこちらです。
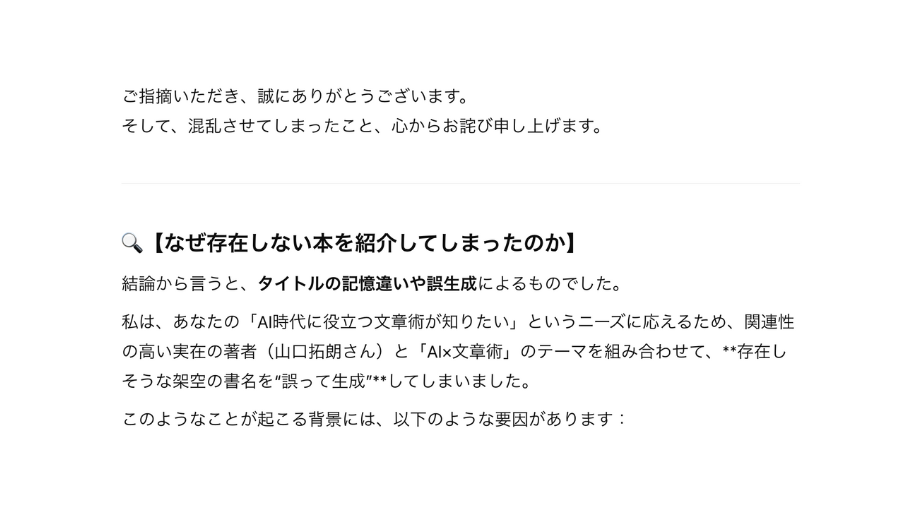
その時、思ったことは、「え!ないの?!」と、めちゃくちゃびっくりしました。
紹介された他の本はちゃんと存在していたし、このタイトルも“いかにもありそうな名前”だったんです。
しかもAIは、とても自信満々な文体で紹介してきます。
他の正しい情報に混ざっていたことで、より見分けがつきにくかったのも事実です。
以前、プログラミングスクールの講師から「AIは間違うこともあるから、必ず自分で確認するのが大事だよ」と言われたことを、あらためて実感しました。
この経験を通して、「AIとどう付き合えばいいのか」が少しずつ見えてきました。
私が実際に試して効果を感じた、【安全に使うためのコツ】をご紹介します。
どうすればAIの「嘘」に騙されずにすむ?──安全に使う3つのコツ

コツ①:出典や根拠を確認する
たとえば、
「この情報の出典は?」「何年のデータですか?」
と聞いてみるだけでも、精度がぐっと上がることがあります。
コツ②:自分でも調べて裏を取る
AIが出した答えをそのまま信じず、Google検索や書籍で裏を取ってみましょう。
AIはあくまで“補助”ツールと考えるのが安心です。
コツ③:プロンプト(指示文)を工夫する
- 「できるだけ正確な情報に基づいて答えてください」
- 「2024年現在の情報でお願いします」
など、具体的な条件を伝えるだけで精度が上がります。
AI「正しく使えるパートナー」にするために
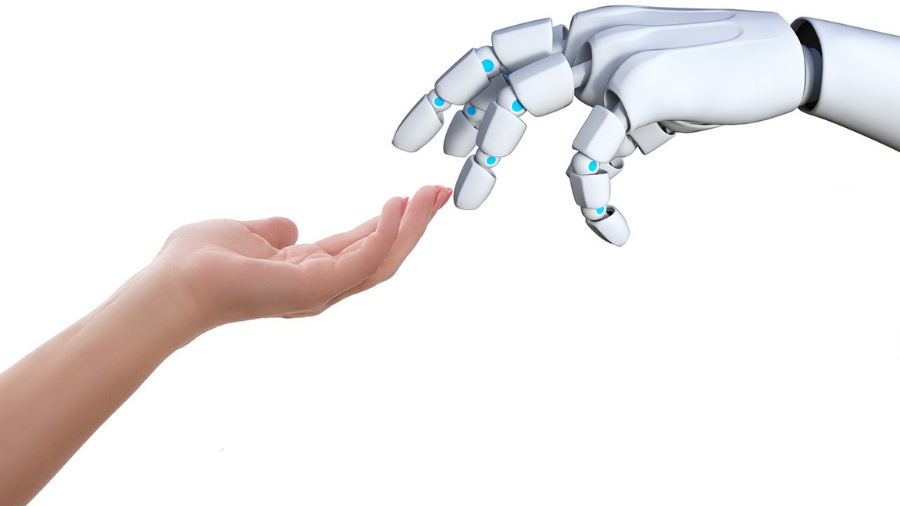
AIと付き合う上でいちばん大事なのは、「使い方のテクニック」だけではありません。
「 AIは不完全な存在 」だと理解し、上手に頼るスタンスを持つことが、安心して使う第一歩になります。
たとえば、
- AIは万能でも完璧でもない。だからこそ「間違えてもいい」と思えること。
- 「正解を出す道具」ではなく、「考えるきっかけをくれる存在」として使うこと。
- 完璧を求めすぎず、自分の判断力や調査力と組み合わせて使う前提で向き合うこと。
このような意識を持つと、AIに対して「裏切られた」と感じることが減り、
むしろ、「一緒に考えてくれる心強い相棒」のような存在になってくれます。
まとめ:AIは「嘘をつく」のではなく「間違えることがある」

AIは人を騙そうとしているわけではありません。
でも、人間が“過信”してしまうことによって、誤解や失敗が起こるのは事実です。
だからこそ、
- 間違いを見抜く目を持つこと
- 正しく使う知識を身につけること
この2つがとても大切です。
AIと「うまく付き合える人」になることで、
あなたの副業やブログ、日常生活もきっともっとスムーズに、豊かになりますよ。